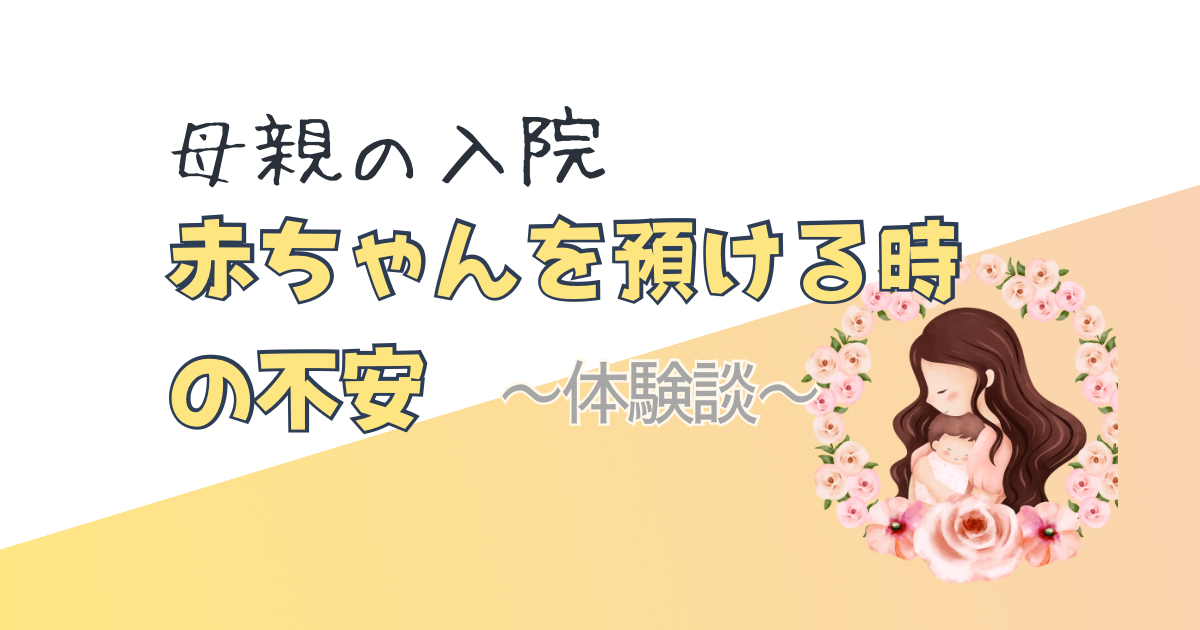母親の入院で赤ちゃんを預けることになった不安
『治療のための約1ヶ月半の入院』
その一言を聞いた瞬間、末っ子をどうすればいいのか頭が真っ白になりました。
まだ赤ちゃんだった末っ子。
私の入院中、誰がこの子の面倒を見てくれるのだろう。
大好きな子どもたちと離れるのがつらくて、不安で夜も眠れませんでした。
それでも、治療を続けるためには預けるしかない――。
そんな現実に向き合わざるを得ませんでした。
上の子たちは義父母宅へ。赤ちゃんは実家に預けることに
以前、上の子(小学生)を義父母宅に預けたことがありました。
そのとき義父母も、本当にいっぱいいっぱいで頑張ってくれていました。
それでも、小学生の面倒を見るだけでも手一杯だった様子が今でも忘れられません。
「赤ちゃんまで一緒に預かって」とは、到底お願いできない状況でした。
上の子たちも義父母も、みんなそれぞれに精一杯だった。
だからこそ、末っ子の預け先は別に探すしかありませんでした。
赤ちゃんを実家に預けるメリットとデメリット
私の実家には、現役で保育士として働いている母がいました。
母が勤める保育所で預かってもらえることになり、保育所のスタッフと一緒に赤ちゃんを見てくれる環境が整っていたんです。
「赤ちゃんを連れて行っても大丈夫だよ」
母がそう言ってくれたとき、心の中に少しだけ光が差した気がしました。
慣れない場所でも、母がそばにいてくれるなら赤ちゃんも安心できるかもしれない――。
そう思えたのは、家族の協力があったからこそでした。
預け先での保育環境(保育所でのケア体制)
私の入院中、末っ子を実家に預けることに決めたのは、やはり安心できる環境があったからでした。
実家には、現役で保育士として働く私の母がいて、保育所で子どもを預かってもらえる環境が整っていました。
赤ちゃんを預けるとき、まず一番に気になったのは「しっかりお世話してもらえるかな」という不安でした。
実際に母の勤める保育所では、0歳児の受け入れ体制が整っていて、スタッフさんも慣れているので安心感がありました。
保育所に通っている他の子どもたちの中で、赤ちゃんも自然と生活リズムが整っていくように感じました。
具体的には、赤ちゃん用のベッドや哺乳瓶の準備、離乳食の進み具合に合わせたメニューなど、細かいところまでサポートしてもらえました。
母も「いつでも連絡してね」と言ってくれて、私自身がすぐに状況を把握できる体制が心強かったです。
こういった安心できる保育環境があったことで、入院に集中することができ、気持ち的にもだいぶ救われました。
もし実家や近くの保育所などに同じような環境がある方は、迷わず相談してみるのがおすすめです。
私のように「赤ちゃんを預けるのは心配」という方でも、実際の保育体制やサポートが整っている場所なら、安心して預けられるかもしれません。
▶︎ポイント
✅ 保育所での赤ちゃんの受け入れ体制
✅ スタッフさんや保育環境がしっかり整っていた
✅ 離乳食や授乳など、細かなところまでサポートあり
✅ 連絡体制があって安心できた
この体験をしたからこそ、同じような状況の方へお伝えできる情報があります。
次回の記事では「赤ちゃんを実家に預けるときの準備リスト」について、私自身が感じたリアルなポイントをまとめていきますね!
赤ちゃんを預けるときに感じた不安と乗り越えた方法
「ママがいない間、ちゃんと安心して過ごせるかな?」
「泣いてばかりで誰も手に負えなくなるんじゃないかな?」
そんな不安が胸いっぱいに広がりました。
特に、赤ちゃんは夜泣きや母乳、ミルク、離乳食…全部が心配の種。
でも、実際に預ける直前になると、準備を整えることで少しずつ心が落ち着いてきました。
私がしたことは:
✅ 赤ちゃんの生活リズムを母子手帳のメモ欄にまとめて母と共有
✅ お気に入りのおもちゃや、においのついたタオル類を一緒に持参
実家に預けた後も、毎日状況を写真や動画を撮って送ってもらいました。
母の「大丈夫よ、安心してね」の一言に何度も救われたのを覚えています。
こうしてみると、不安をゼロにすることはできなかったけれど、事前の準備と信頼関係、そして連絡体制が一番の心の支えになりました。
同じような境遇の方へ
もし、今この記事を読んでくださっている方の中に、同じように「赤ちゃんを預けないといけない」状況にある方がいたら、少しでも不安を減らしてほしいと思います。
次回の記事では、**「赤ちゃんを実家に預けるときの準備したもの」**について、私の実体験をもとに【完全版リスト】をお届けしますね。
私が実際に使って便利だったグッズも合わせてご紹介するので、ぜひチェックしてみてください!
まとめ
預ける決断は、想像以上に勇気が必要でした。
でも、家族の支えや周りの協力があったからこそ、少しずつ自分を責めないでいられるようになりました。
「私だけじゃない、同じように悩む人がいる」
そんな風に思ってもらえたらうれしいです。
このブログでは、私が経験したことを通して、同じような方に少しでも安心を届けられるように、これからも書き続けていきたいと思います◌̥*⃝